クラゲや脳のない生物が動く仕組み
クラゲは、化石が発見されているだけでも5億年、学説では10億年前からほとんど姿を変えずに地球上に存在していたとも言われている古代からの生物です。

クラゲには、脳はありません。
代わりに、体中に「散在神経系」と呼ばれる神経が体全体、網目状に広がっています。
この神経系によって、クラゲは水流や物体に触れた時に反射的に動くことができます。
クラゲには、脳だけでなく心臓や血管も存在しません。
血管の代わりに「水管」と呼ばれる管が通っており、水管によって体中に栄養分が運ばれる仕組みになっています。
心臓がポンプの役割は、クラゲ自体。傘を開閉させることによって、全身に栄養を送っています。
さらには、動物界から分岐した種であるハコクラゲの一種は、脳を持たないながらも学習能力を有することを示す論文が2023年9月22日に発表された。
その研究では、ハコクラゲから視覚ニューロン(神経細胞)を取り出し、皿に移して調べた。細胞は、衝突を表す小さな電気信号を受信しながら、しま模様の画像を見せられた。細胞は5分以内に、ハコクラゲを方向転換させる信号を送り始めた。
また、中枢神経をもたないクラゲは睡眠をとることも発見され、睡眠は脳のみでなく、末梢においても何らかの役割を果たしていることを示している。
ゆえに、脳の回復ではなく細胞の回復に必要なのが睡眠なのかもしれない。
微生物もヒトも、生きるために電気を使う仕組みはほぼ同じ
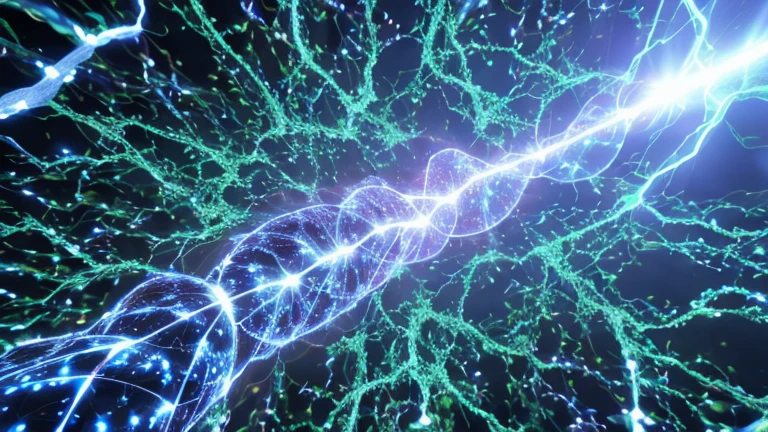
多くの生物は、細胞内に持っている「電子回路」を使って「呼吸」をすることで、生命活動に必要なエネルギーを得ています。具体的には、エネルギーの貯蔵や放出を行う「ATP」(アデノシン三リン酸)という物質を作るために電子回路、「電子伝達系と言われる電子が自然に流れる現象」を使います。
よって、生き物、ヒトに限らず植物なども含めて脳よりも「細胞の電子伝達」が動くことに極めて重要ということです。
ビタミンCの発見で知られる生化学者のセント・ジョルジ・アルベルトは「“Life is nothing but an electron looking for a place to rest.” (生命というのは、電子が(熱力学的に)落ち着ける場所を探していることにほかならない)」という言葉を残しています。
電子の流れを使って生命活動に必要なエネルギーを獲得する仕組みは、何からどう電子を取り出すのか、システムの細部についてはどの生物も同じというわけではありません。
ヒトは有機物と酸素ですが、微生物の中には、硫黄や水素など有機物以外の物質から引き抜いた電子を回路に投入するものもありますし、酸素以外のものを使って電子を取り出すものもあります。
更には生命活動に必要なはずの電気(電子)を、捨てたり食べる微生物も発見されています。
こうした「電気微生物」はJAMSTEC超先鋭研究開発部門の鹿島裕之研究員をはじめとして研究されており、再生可能エネルギーのひとつとして、田んぼや廃水の中などに棲息している電気微生物を利用して発電する微生物燃料電池の研究開発も国内外で行われています。

